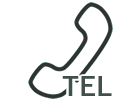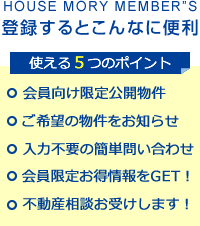逗子・葉山・鎌倉の土地・戸建て情報満載!不動産を探すならハウスモリーへ。
逗子・葉山・鎌倉の土地・戸建て情報満載!不動産を探すならハウスモリーへ。
逗子・葉山・鎌倉通信Areareport
鎌倉の街の中心であり、「鎌倉」の象徴でもある「鶴岡八幡宮」。
鎌倉幕府を開いた源頼朝により
鎌倉のまちづくりの中心に据えられたのは1180年(治承4年)
そのまま現在に至ります。
しかしながら鶴岡八幡宮の御由緒を辿ると
頼朝より100年以上遡った1063年(康平6年)に
源頼義が京都の石清水八幡宮を勧請し
「由比若宮」(元八幡)を創建したのがその始まりと伝わっています。
・
源頼義とは?そもそも源氏と鎌倉の関わりはどのように始まったのでしょうか。
・
源頼義は河内源氏の二代目棟梁で本拠地は関西です。
清和天皇の血を引く「清和源氏」の一族で
河内国(今の大阪府羽曳野市)を拠点とした事から河内源氏と称されています。
・
河内源氏の祖は頼義の父・源頼信です。
1028年、関東房総三カ国(上総国、下総国、安房国)で平忠常が乱を起こします。
はじめに桓武平氏(国香流)嫡流の平直方が
朝廷から討伐を命じられますが治めることができず
1030年(長元3年)に源頼信が討伐を命じられ
息子の頼義とともにこれを平定します。
この乱を平定した事で坂東武士の多くが頼信の配下に入り
河内源氏が東国に進出する足がかりができます。
・
さらに、武勇を見込まれた頼義が、平直方から娘の婿にと請われます。
鎌倉を本拠地としていた直方は、鎌倉の大蔵にあった邸宅や所領
桓武平氏嫡流伝来の郎党をも頼義へ譲り渡します。
関西を本拠地としていた河内源氏の東国での基盤
そして源氏と鎌倉の繋がりがここに生まれます。
・
その後、奥州で反乱を起こした安部氏討伐の勅命を受けた頼義は
坂東武者と共に奥州へ向かいます。
長き苦戦の末ようやく勝ったこの戦は
歴史上「前九年の役」(1051年〜1062年)と呼ばれています。
頼義は出陣の際に、源氏の氏神である京都の「石清水八幡宮」に戦の加護を祈願していたので
奥州平定のお礼として1063年(康平6年)、由比ヶ浜辺に石清水八幡宮を勧請しお祀りしました。
この時に創建されたのが「由比若宮」(元八幡)、後の鶴岡八幡宮です。
・
その117年後の1180年(治承4年)、源氏を再興し棟梁として
先祖ゆかりの地・鎌倉入りした源頼朝は、早速先祖由来の「由比若宮」を現在の地に遷し
「鶴岡八幡宮」を造営、これを鎌倉武士の守護神として篤く祀りました。
1191年(建久2年)には鎌倉幕府の宗社にふさわしく上下両宮の現在の姿に整えられ
武家の都・鎌倉のまちの中心となりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで源氏の起源もおさらいしてみます。
源氏の本拠地は元々は関西、清和天皇が祖と言われています。
清和天皇の孫にあたる経基王が臣籍降下し「源姓」を賜り源経基と名乗り
「清和源氏」(せいわげんじ)の初代となります。
ちなみに、桓武天皇の血筋から臣籍降下し平姓を賜った平高望の系統の武士団が
「桓武平氏」(かんむへいし)です。
また、源氏は清和天皇他21人の天皇の子孫が源姓を名乗りこれを
源氏二十一流(村上天皇ー村上源氏など)と言います。
・
経基の子・満仲は、摂津国川辺郡多田(現 兵庫県川西市多田)を本拠地にし
摂津源氏と呼ばれる武士団を形成していきます。
・
満仲の息子には大江山の酒呑童子退治や四天王を従えたことで有名な源頼光がいます。
彼は長男で本拠地を引き継ぎ摂津源氏を率い、その孫から多田源氏が興ります。
満仲の次男・源頼親の系統は大和国宇野(現 奈良県)を本拠地としたことから
大和源氏と呼ばれる武士団を
三男・源頼信の系統は河内国壷井(現 大阪府羽曳野市壷井)を本拠としたことから
河内源氏と呼ばれる武士団を形成します。
(頼朝は河内源氏の流れをくみます)
・
河内源氏の初代棟梁の源頼信は、関東で起きた平忠常の乱を平定
二代目棟梁の頼義(鶴岡八幡宮の前身「由比若宮」創建)は父と共に平忠常の乱を討伐し
その後奥州安部氏の反乱を平定(前九年の役)
三代目棟梁の義家は父と共に前九年の役に参戦し
その後奥州清原氏の内紛(後三年の役)を平定しました。
こうした武功は源氏の武家としての存在感を大きくしました。
・
ただ後三年の役に関しては、清原氏の内紛を治めたいわば私戦であると朝廷からみなされ
勅旨ではないので恩賞がでず、役職も解任されてしまいます。
義家は共に戦った坂東武者達に報いるため、私財から恩賞を出しました。
このことが却って関東における源氏の名声を高め
後の源頼朝による鎌倉幕府創建の礎となったともいわれています。
・
その後、河内源氏は内紛などもあり
一方で白河法皇や鳥羽法皇の寵愛を受けた
伊勢平氏の平正盛・忠盛父子、美濃源氏の源光保・光宗父子らが復興し
武門の中で河内源氏の勢力は相対的に低下していきます。
・
ここから摂関家や天皇・上皇(法王)も加わった
複雑で悲劇的な源平合戦へと向かっていくことになります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●左:鶴岡八幡宮正面にある三ノ鳥居
●右:参道から舞殿と上宮を望む
舞殿の場所にはかつて若宮があり、その回廊で1186年(文治2年)に
源義経の愛妾・静御前が舞いを披露したと言われています。
・
頼朝の追っ手がかかった義経と静御前は吉野山で別れ別れになります。
捕らえられた静御前は鎌倉へ送られ、頼朝に鶴岡八幡宮で白拍子の舞を命じられます。
日本一の白拍子と謳われた静に、頼朝は鎌倉幕府の繁栄を願う舞を望んでいましたが
静が披露したものは、義経を慕う歌と舞でした。
・
「吉野山 峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき」
(吉野山の峰の白雪を踏み分けて、山奥深く入っていった義経様のあとが恋しい)
「しづやしづ しづのをだまき くり返し 昔を今になすよしもがな」
(糸を繰り返し巻いて出来る苧環(おだまき=糸を玉状に巻いたもの)のように
あの人が静、静と呼んでくれた頃に時を巻き戻せないものかしら)※訳には諸説あり
・
その舞と歌声に見ていたものは皆感動しますが、頼朝の逆鱗に触れます。
しかし妻の政子が、静の胸中に感じるところがあり
(頼朝が挙兵した頃は政子も頼朝の身を案じ
不安な日々を過ごしていた事を思い出したのでしょうか)
頼朝を説得して事なきを得ます。
頼朝は卯花重(うのはながさね)の衣を脱いで静に与え
静はこれをうち被り退場したと言われています。
●左:源平池
三ノ鳥居の先に広がる池。
8月の早朝に咲き誇るハスの花の様子は、鶴岡八幡宮の夏の風物詩の一つ。
太鼓橋を挟んで東側(向かって右側)が源氏池
西側(向かって左側)が平家池と呼ばれています。
・
この池には源氏池に三つ、平家池四つの島がありますが
これは三(さん)=産で源氏の繁栄を
四(し)=死で平家の滅亡を祈願したためと伝わっています。
●右:鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム
開館:午前10時〜午後4時半(最終入場 午後4時)
・
鶴岡八幡宮のことはもちろん、年間を通して
歴史や文化、文学、美術など幅広いテーマを取り上げ
国内外の方に鎌倉の魅力を発信する新たな文化交流施設。
《概要》
●主祭神:応神天皇(おうじんてんのう)・比売神(ひめがみ)・神功皇后(じんぐうこうごう)の三柱
●例祭日:9月15日
●所在地:神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31
●交 通:JR横須賀線「鎌倉」駅東口徒歩10分
●駐車場:午前9時〜午後7時30分(1時間まで600円、以降30分毎300円)
※ご祈祷を受ける方は2時間まで無料(受付に申し出)
●主施設:本宮・舞殿・大石段・大銀杏跡・宝物殿(大人200円/小人100円)・源平池・太鼓橋・神苑ぼたん庭園・流鏑馬馬場・手水舎・白旗神社・祈祷受付・車祓所・喫茶「風の杜」・休憩所等
※境内には、鎌倉の寺社が所有する文化財を集め収蔵している「鎌倉国宝館」、「鶴岡幼稚園」もあります。
※令和元年(2019年)6月8日、旧「神奈川県立近代美術館 鎌倉館」の建物を継承した「鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム」がオープンしました。(入場料は展示により異なります)