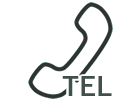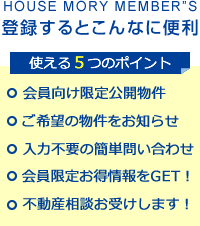逗子・葉山・鎌倉の土地・戸建て情報満載!不動産を探すならハウスモリーへ。
逗子・葉山・鎌倉の土地・戸建て情報満載!不動産を探すならハウスモリーへ。
逗子・葉山・鎌倉通信Areareport
若宮大路は、源頼朝によって造営された鶴岡八幡宮の参道です。
1180年(治承4年)10月6日、鎌倉入りを果たした源頼朝は、まず先祖の源頼義が京都の石清水八幡宮を勧請し創建した「由比若宮」(当時由比郷にあった鶴岡八幡宮の前身)を、現在の鶴岡八幡宮のある小林郷北山に遷座して「鶴岡八幡宮新宮若宮」(現鶴岡八幡宮)としました。
この鶴岡八幡宮を内裏に見立て街づくりの中心とし、平安京の朱雀大路を模して造営されたのが若宮大路です。
若宮大路は鶴岡八幡宮から由比ガ浜まで一直線に延び、武士の都・鎌倉の軸であり、街づくりの中心線であり、海岸側から一の鳥居、二の鳥居、三の鳥居と三つの鳥居が並ぶ参道です。
その若宮大路の中央に、一段高くなった形状の参道があります。それが「段葛」です。
1182年(養和2年)、頼朝が妻政子の安産祈願のために造営したと言われており、頼朝自らが指揮をとり、北条時政や有力御家人達が土や石を運んだと『吾妻鏡』(鎌倉幕府の歴史書)に記されています。
段葛は“葛石”を積み上げて造られた事から、そう呼ばれるようになったのだそうで、石を置いて造られた道なので置道、置石と呼ばれたりもします。
また段葛の作りは、鶴岡八幡宮に近くなるにつれて道幅が狭くなり、両側の土手の高さも低くなっています。
これは「遠近法」を利用して、段葛が長く鶴岡八幡宮が遠くに見えるよう錯覚させるためと言われています。
このトリッキーな作りは、攻め入った敵に鶴岡八幡宮まで距離があるように思わせる為の軍事上の策、もしくは参道を長く立派に見せるための策として用いられたようです。
段葛は、現在は三の鳥居から二の鳥居までの約500m程の長さですが、造営された当時は三の鳥居から一の鳥居まで通じていたと言われています。
江戸時代に現在の下馬辺りまでとなり、さらに明治期に横須賀線の開設に伴い二の鳥居辺りまでが撤去されました。
段葛は、道の中央に盛り土をし両側を石を積んで押さえて更に道を造成した独特の構造をしています。
鎌倉時代に造られたあと、近世に幾度も作り直されていますが、平成には一年半を掛けた大改修工事が行われました。
路面は舗装され歩き易くなり、左右の桜やツツジは植え替えられ、石灯籠も一新されました。
2016年(平成28年)3月に完成し、通り初めは歌舞伎役者の中村吉右衛門さんらが参列し、賑々しく行われました。
現在は桜の木も大分大きくなり、お花見や緑を楽しめる程に育っています。